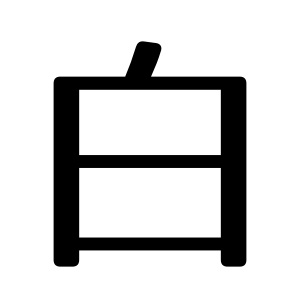
この記事を書いた人: 「白物家電ブログ)」管理人
家電量販店での商品案内歴約20年(現役)。
ブログ運営10年以上、YouTubeチャンネル登録者3.3万人。
家電を買って試したり、データや仕組みに基づいて深堀りして考えるのが好きです。
YouTube▶白物家電チャンネル
エアコンを取りつけるのは大掛かりだし、灯油を使うのも避けたい。
「それなら、オイルヒーターを買ったら良いんじゃないか? 」と考え、ネットで情報収集する方は多くいるはずです。
そして、ネット記事やYouTube動画なんかをみてみると、判で押したように「陽だまりのような暖かさ」「空気が乾燥しにくいクリーンな暖房」なんて、やたら魅力的な言葉で紹介されていますよね。
でも、ちょっと待ってください。 そのイメージ、もしかしたら“心地よい誤解”かもしれません。
今回は、一部で根強く支持されているオイルヒーターについて、その宣伝文句の裏側を、仕組みやデータに基づいて冷静にチェックしていきたいと思います。
「高かったのに、思ったより暖かくない…」なんて後悔をしないために、ぜひ最後までお付き合いください。
まずはおさらい。オイルヒーターの“よく聞く評判”って?
さて、本題に入る前に、皆さんがネットやお店で一度は目にしたことがあるであろう、オイルヒーターの“売り文句”をいくつかおさらいしてみましょう。
- 「陽だまりのような、ムラのない暖かさ」
- 「空気が乾燥しにくい、クリーンな暖房」
- 「無音・無風で、寝室にも最適な快適さ」
- 「表面温度が熱くなりすぎず、安全性が高い」
どれも魅力的で、なんだかすごく良さそうな暖房器具に思えますよね。
でも、ちょっと待ってください。 これらの宣伝文句をよく見てみると、あることに気づきませんか?
そう、これらはすべて「どんな風に暖かいか」という暖かさの“質”については語っていますが、肝心の「どれくらい部屋を暖められるのか」という暖かさの“量(パワー)”については、あまり触れられていないんです。
そして、多くの人が一番気になるであろう「電気代」についても、あまり積極的に語られてはいませんよね。
この記事では、まさにその「語られていない部分」に焦点を当てて、オイルヒーターの本当の実力を、仕組みやデータに基づいてチェックしていきたいと思います。
目次
大前提:1500Wのヒーターは、どれも同じ熱量しか出せない
まず、一番大事なことからお話しします。
オイルヒーターだろうと、セラミックファンヒーターだろうと、どんな電気ヒーターでも、消費電力が同じであれば、生み出せる熱の量(カロリー)は全く同じです。
これは物理の法則なので、本体価格が高い・安いとか、メーカーがどこなどにかかわらず変わりません。
電気を熱に変える効率(COP)は、どの電気ヒーターも例外なく「1.0」。
つまり、1の電気を使ったら、1の熱しか生み出せないんです。
「じゃあ、なんであんなに暖かさの感じ方が違うの?」と思いますよね。
その秘密は、生み出した熱を「どうやって部屋に届けるか」という方法の違いにあります。
セラミックファンヒーター
ドライヤーのように、ファンで温風を強制的に送り出す(強制対流)。だから速くてパワフルに感じる。
オイルヒーター
本体をじんわり暖め、そこから出る赤外線(輻射熱)と、暖まった空気が自然に上昇する流れ(自然対流)で、ゆっくり部屋全体を暖める。
この「熱の届け方」の違いが、オイルヒーターのメリットと、そして大きな弱点を理解する上で、めちゃくちゃ重要になってきます。
セールストークを冷静にチェック!オイルヒーターの“心地よい誤解”
それでは、オイルヒーターの宣伝でよく使われるフレーズを、一つひとつ見ていきましょう。
トーク①:「陽だまりのような、ムラのない暖かさ」は本当?
【結論から言うと…】本当です。ただし、それはオイルヒーターが「贅沢な暖房」であることの証明でもあります。
◎ たしかに、ここがスゴい!「輻射熱」がもたらす上質な暖かさ
輻射熱は、風と違って壁や床、天井、そして人体に直接熱を届けます。
暖められた壁や床からもまた熱が放出されるので、部屋全体が均一な温度になり、まるで春の日差しを浴びているような、心地よい暖かさを感じることができます。
これは事実ですし、他の暖房器具ではなかなか真似できない、オイルヒーターだけの価値です。
△ でも、ここは知っておきたい!快適さと引き換えの大きなリスク
しかし、この最高の快適性を手に入れるには、大きな代償とリスクが伴います。
リスク①
とにかく暖まるのが遅い
まず本体内部のオイルを暖め、次に本体を暖め、そして部屋全体を暖める…という手順を踏むため、部屋が暖まったと感じるまで30分~1時間かかることもザラです。
リスク②
いざという時の「避難所」がない
ここが他の電気暖房との決定的な違いです。
セラミックファンヒーターやカーボンヒーターは、たとえ部屋全体が寒くても、その前に陣取ればとりあえず暖かい「避難所」になります。
しかし、オイルヒーターにはそれがありません。部屋全体を均一に暖めるという思想のため、局所的に強く暖めてはくれないんです。
つまり、もしお家の断熱性能が低かったり、部屋の広さに対してパワーが足りなかったりすると、「部屋のどこにいても、ずーっと肌寒い」という状態に陥ります。
条件が揃えば最高、でも一つでも欠けると全く役に立たない。
それがオイルヒーターの「オール・オア・ナッシング」な特性なんです。
トーク②:「空気が乾燥しにくい」は本当?
【結論から言うと…】これは半分本当で、半分は誤解を招く表現です。
◎ たしかに、ここがスゴい!風がないから「肌の乾燥を感じにくい」
まず「YES」の側面から。エアコンやファンヒーターのように温風を直接体に当てないので、肌の水分が奪われにくいです。
その結果、「肌の乾燥を感じにくい」というのは、体感として事実です。
喉が弱い方や、肌の乾燥が気になる方にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。
△ でも、ここは知っておきたい!物理的には「空気は乾燥する」
一方で「NO」の側面。そもそも、空気の乾燥度合いを示す「相対湿度」は、室温が上がるだけで必ず下がります。
空気は、温度が高いほどたくさんの水分を含むことができます。暖房で室温を上げるということは、空気というコップを大きくするようなもの。
中の水の量(絶対湿度)が変わらなければ、コップが大きくなった分、満杯率(相対湿度)は下がってしまうんです。
これは物理現象なので、オイルヒーターだろうとエアコンだろうと関係ありません。
つまり、「オイルヒーターは空気が乾燥しにくい」という宣伝文句が本当だとするなら、それは、「大して部屋の温度が上がってないから、部屋の湿度が下がらない」と言っているのと、ある意味では同じことになってしまいます。
なぜオイルヒーターは電気代が高くなりがちなのか?
「同じ熱量なら電気代は同じはずなのに、なぜオイルヒーターは電気代が高いイメージがあるの?」という疑問。
ここが気になっている方は多いはずです。
答えは、オイルヒーターが「電気代が高くなる使い方」を前提に設計されているからです。
思い出してみてください。
電気ヒーターは、電気を熱に変える効率が「1」しかない、いわば燃費の悪い暖房です。
一方で、エアコンは電気の3倍以上の熱を生み出せる、燃費の良い暖房です。
この大前提に立つと、エネルギー効率の悪い電気ヒーターは、本来、部屋全体を暖めるようなメイン暖房には向いていません。
それこそ「ホットプレートやヘアドライヤーで部屋を暖めようとする」ような、とても効率の悪いな試みとも言えます。
電気ヒーターの合理的な使い方は、あくまで局所的なスポット暖房です。
しかし、オイルヒーターはその思想に逆行し、「部屋全体を均一に暖める」ことを目指しています。
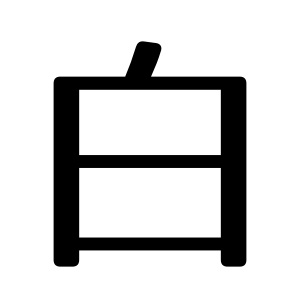
燃費の悪いエンジンであるにも関わらず、「長距離ドライブもおまかせあれ」みたいに言ってるようなチグハグさがあります。
結果として、長時間にわたって多くの電力を消費することになり、電気代が高くなりやすいのは必然と言えます。
最大の問題点:「最大13畳」を鵜呑みにしてはいけない、厳しい現実
そして、私がオイルヒーターの売り方で一番「フェアじゃないな」と感じるのが、この「適用畳数」の表記です。
2つの基準が混在する「適用畳数」の表記
デロンギなどの製品ページを見ると、「最大13畳対応!」といった大きな文字が目に入ります。
これを見ると、「うちのリビングでも使えるかも!」と思ってしまいますよね。
でも、そのページの隅っこをよーく見ると、小さな文字で「※日本電機工業会自主基準では約10畳まで」なんて書いてあったりします。
日本電機工業会(JEMA)自主基準(例:10畳)
こちらが、メーカーが違っても同じ物差しで比較できる、信頼性の高い数字です 。
デロンギ独自基準(例:13畳)
これは、業界統一のJEMA基準よりも、さらに断熱性の高い住宅など、より恵まれた条件下で測定された参考値であると推測されます 。
まず、信じるべきは後者の「JEMA基準」である、ということを覚えておいてください。
その「JEMA基準」ですら、大きな“ワナ”がある
しかし、話はこれだけでは終わりません。ここからが一番重要なポイントです。
実は、同じ「JEMA基準」でも、暖房器具の種類によって、前提としている家の性能が全く違うんです。
エアコンやファンヒーターの適用畳数
実はこれ、1964年に作られた基準を元にしており、「無断熱の木造住宅」を想定しています 。
断熱材が入っているのが当たり前の現代の家にとっては、かなり厳しい条件での表記なので、ほとんどのご家庭でカタログ通りの性能が期待できます。
オイルヒーターなど電気ヒーターの適用畳数10畳表記
一方、こちらは「断熱材50mmのコンクリート住宅」という、ある程度理想的な条件を前提に算出されています 。
つまり、エアコンの「10畳用」と、オイルヒーターの「10畳用」は、全くの別物なんです。
もし、オイルヒーターをエアコンと同じ土俵、つまり「無断熱の木造住宅」で使った場合、JEMAの基準表に当てはめると、その適用畳数はわずか「約3畳」になってしまいます 。
これが、「カタログでは10畳用って書いてあったのに、全然暖かくない…」という後悔が生まれる、最大のからくりです。
▼1200Wの電気暖房の適用床面積目安
| 断熱材 | コンクリート住宅 | 木造住宅 |
| なし | 約4.5畳まで | 約3畳まで |
| 50mm | 約8畳まで | 約6畳まで |
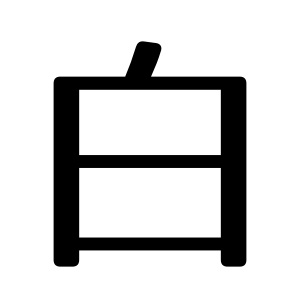
エアコン・石油ファンヒーターの畳数表記は無断熱の住宅の想定です。
同じく無断熱の住宅の場合、オイルヒーターの適用床面積の目安は3畳までとなります。
日本の住宅の「断熱性能」という不都合な真実
「じゃあ、最新の高性能な家なら大丈夫なんでしょ?」と思いますよね。
ネットの口コミやYouTubeの動画なんかでは、「オイルヒーターでも充分暖かい」という意見はよく見かけますし、実際にオイルヒーターだけで不満なく過ごせるケースもあります。
ですが、それは割と条件がいい場合の話ということになります。
だれにでも当てはまるわけではないので、その点には充分にご注意ください。
ちなみに、日本の住宅ストックのうち、2025年から義務化された「断熱等級4」以上の家は約2割程度しかありません。
一方で、無断熱相当の住宅は25%くらいあります。
少し古いですが、参考資料を貼って起きます。
参考ページ
脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方について
国土交通省 近畿地方整備局 住宅整備課 令和3年10月
さらに言えば、この計算は東京のような温暖な地域を想定したものです。
東北のような寒冷地では、家から熱が逃げるスピードが速いので、さらに厳しい条件になります。
北海道と青森・岩手・秋田あたりの方は、そもそもあまりオイルヒーターの導入は検討しないと思います。
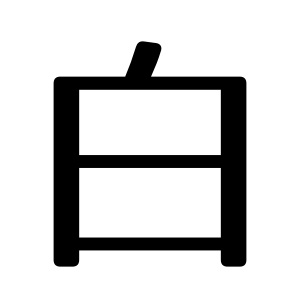
宮城、山形、福島あたりだと、わりとオイルヒーターも候補にする方がいると思いますが、そのあたりの地域だと一層厳しいと思います。
【補足】オイルレスヒーターってどうなの?
ところで、最近よく聞く「オイルレスヒーター」ってどうなの?と思った方もいるかもしれません。
これは名前の通りオイルを使わないヒーターで、オイルヒーターの進化版のような立ち位置の製品です 。
オイルヒーターの最大の弱点だった「暖まるのが遅い」「重い」という点を改善するために開発されました 。
- 速暖性が高い: オイルを介さず直接フィンや空気を暖めるため、オイルヒーターの約2倍の速さで暖まります 。
- 軽量: オイルが入っていない分、本体が軽く、部屋から部屋への移動が楽です 。
その代わり、オイルヒーターの強みであった**「蓄熱性」(電源オフ後の余熱)は劣ります** 。
ただし、根本的な仕組みはオイルヒーターと同じ電気抵抗ヒーターなので、消費電力が大きいという点は変わりません 。
オイルヒーターと同じく、その性能を発揮するには高い住宅性能が求められる、という点も同じです。
まとめ:オイルヒーターは「暖房能力」ではなく「快適性」にお金を払う贅沢志向
ここまで見てきた通り、オイルヒーターは「誰にでもおすすめできる万能な暖房」では決してありません。
むしろ、その性能を100%引き出せる人が、限定される贅沢な暖房器具なんです。
その数万円という本体価格は、パワフルな暖房能力への対価ではありません。
それは、「無音・無風」という他の暖房器具にはない、卓越した快適性を手に入れるための対価なのです。
そして、その快適性を享受するためには、高い電気代がかかることを覚悟し、かつ、ご自身の家が気温の低い地域ではなく、さらにその環境に見合った断熱性を持っている必要があります。
オイルヒーターは、その高価な価格と美しい宣伝文句から、「最も性能の良い電気暖房」という誤解をされがちです。
しかし、その本質は「熱の運搬力を捨てて、快適性に全振りした暖房器具」。
そのピーキーな特性と、性能を発揮するための厳しい条件をしっかり理解した上で選ばないと、「高かったのに、全然暖かくない…」という、最悪の後悔につながりかねません。
この記事が、あなたの暖房器具選びの冷静な判断材料になれば嬉しいです。



