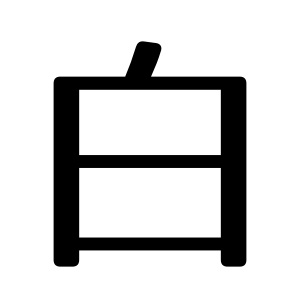
この記事を書いた人: 「白物家電ブログ)」管理人
家電量販店での商品案内歴約20年(現役)。
ブログ運営10年以上、YouTubeチャンネル登録者3.3万人。
家電を買って試したり、データや仕組みに基づいて深堀りして考えるのが好きです。
YouTube▶白物家電チャンネル
冬の乾燥対策で加湿器を検討すると、ネット上で必ずと言っていいほど目にするのが、象印のスチーム式加湿器。
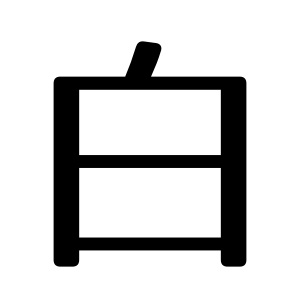
象印のスチーム式加湿器は、本当に「一択」「最強」と言って差し支え無いものなんでしょうか?
ということで、この記事では・・
象印のスチーム式加湿器に付いて、よく聞くメリット・デメリットを再度整理
して行きたいと思います。
関連記事
象印のスチーム式加湿器のラインナップ紹介はこちらのページでしています。
-

-
【2025年版】象印スチーム式加湿器の選び方|シリーズ・モデルごとの違いを一覧表でチェック
2025/11/8
冬の乾燥対策に欠かせない加湿器。中でも、象印のスチーム式加湿器は「手入れが楽で清潔」と長年多くの方に選ばれ続けています。 しかし、いざ選ぼう ...
まずは基本
そもそも「スチーム式加湿器」ってどんなもの?
象印のスチーム式加湿器の例
価格コムの人気ランキング1位(記事作成時点)
象印の加湿器の話に入る前に、まずは「スチーム式」がどんな仕組みなのか、その基本的な特徴を簡単におさらいしておきましょう。
仕組み:
とてもシンプルで、本体の中でお湯を沸かし、その時に出る水蒸気(湯気)で部屋を加湿します。
電気ポットがお湯を沸かすのと同じ原理ですね。
方式としてのメリット
衛生的
水を100℃で沸騰させるので、水の中の雑菌の繁殖を抑えます。だから出てくる蒸気はとてもクリーンです。
加湿パワーがある
温かい蒸気を直接出すので、加湿の立ち上がりが速いのが特徴です。
部屋が冷えにくい
温かい蒸気なので、冬場でも部屋の温度を下げにくいという地味に嬉しい利点もあります。
方式としてのデメリット
電気代が高め
ヒーターでお湯を沸かすので、どうしても他の方式より消費電力が大きくなります。
やけどに注意:
吹き出し口や蒸気が熱くなるので、小さなお子さんやペットがいるご家庭では置き場所に気をつける必要があります。
カルキが付きやすい:
水道水に含まれるミネラル分が、沸騰させることで白い固まり(カルキ)として内部に付きやすくなります。
象印加湿器、ネットの評判をチェック!7つの気になるポイント
それでは本題です。ネットでよく見る象印の加湿器の評判について、一つひとつ掘り下げていきましょう。
気になるポイント①:「手入れが楽」って本当?
【結論から言うと…】日々の「洗いやすさ」は本当
でも「何もしなくていい」わけではない

◎ たしかに、ここがスゴい!「電気ポット」の発想から生まれた洗いやすさ
「象印の加湿器は手入れが楽」と言われる一番の理由はその構造のシンプルさにあると思います。
まさに同社の得意分野である電気ポットの技術が活かされているんですね。
- フィルターがないシンプルな構造:
本体内部はフィルターなどの部品がなく、口が広いので、まるでコップを洗うみたいにスポンジで隅々までしっかり洗えます 。これは他の加湿器にはなかなかない大きなメリットです。
- 汚れがつきにくいフッ素加工
ポットの内側と同じようにフッ素加工が施されていて、水アカなどがこびりつきにくいようになっています 。
この「毎日のお手入れが面倒じゃない」という点が、多くの人に支持されている最大の理由でしょう。
△ でも、ここは知っておきたい!避けられない「カルキ問題」
ただし、「手入れが楽」だからといって「メンテナンスが全く要らない」というわけではありません。
水道水に含まれるミネラル分は、お湯を沸かすと必ず白い固まり(カルキ汚れ)として内部に付着します。
これを放っておくと、加湿能力が落ちたり、沸騰する時の音が大きくなったり、故障の原因になったりもします 。
なので、メーカーは1〜2ヶ月に1回程度のクエン酸洗浄を推奨しています。
手入れしやすいのは確かですが、性能を保つためには定期的なクエン酸でのお手入れは必要、と覚えておくと良いですね。
気になるポイント②:「スチーム式だから衛生的」って聞くけど?

【結論から言うと…】出てくる「蒸気」はとても衛生的
でも「加湿器本体」が常に清潔かどうかは、また別の話
◎ たしかに、ここがスゴい!沸騰させたクリーンな蒸気
スチーム式の大きな強みは、やっぱり衛生面の安心感です。
タンクの水をヒーターで100℃にしっかり沸騰させるため、カビや雑菌が繁殖しにくく、衛生的な蒸気で加湿できるのが大きなメリットです。
部屋に出てくる蒸気はとてもクリーン。小さなお子さんや、体の抵抗力が気になる方がいるご家庭でも安心して使えるのは確かなメリットです。
△ でも、ここは知っておきたい!「蒸気が清潔」と「本体が清潔」はイコールじゃない
ここで少し注意したいのが、「出てくる蒸気がキレイなこと」と「加湿器本体がいつも清潔なこと」を混同しないように、という点です。
例えば、タンクに残った水を何日もそのままにしたり、先ほどのカルキ汚れの手入れをサボったりすれば、当然、本体の中は汚れてしまいます。
本体の清潔さは、やっぱり使う人のお手入れ次第なんですね 。
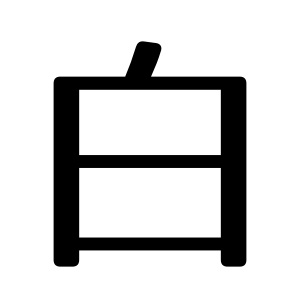
会社の給湯室に湯沸かしポットがあって、中にピンクぬめりや白い粉のようなものが固着している様子を見たことがあるという方も多いはずです。
「衛生的」という言葉が「蒸気」のことを指しているのか、「本体」のことを指しているのか、ちょっと切り分けて考えると良さそうです。
気になるポイント③:「加湿能力がパワフル」って本当?
【結論から言うと…】「スチーム式はパワフル」は完全に間違いというわけではないですが
「パワフル」というイメージだけで広い部屋に使うと、力不足になる可能性が高いです
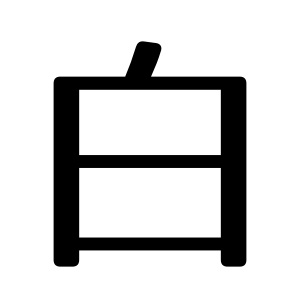
結局は加湿方式よりも加湿能力が重要というわけです
△ まず知っておきたい、「立ち上がり」のイメージとのギャップ
「パワフル」と聞くと、スイッチオンですぐに加湿が始まるイメージがあるかもしれません。
でも、スチーム式は水を沸騰させる必要があるので、実はスイッチを入れてから蒸気が出るまでには少し時間がかかります 。
この点は、ミストがすぐに出る超音波式などとは違うポイントです 。
△ LDKで使うには要注意!「加湿量」で見る本当の実力
本当の意味でのパワフルさ、つまり部屋全体を潤す能力は「加湿量(ml/h)」というスペックで判断することがとても重要です。
象印の主力モデル(EE-DC50やEE-RR50)の最大加湿量は480ml/h。
これは木造なら8畳、プレハブ洋室なら13畳が適用床面積の目安です 。
寝室や書斎なら十分な性能ですが、最近の広めのLDKで使うには、正直なところ力不足になるケースが多いです。
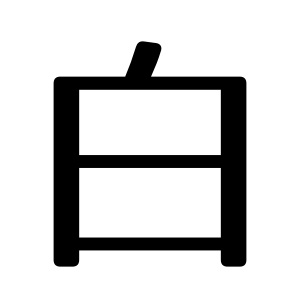
他のメーカーでは、LDK向けに加湿量700ml/h~1200mll/hもラインナップがありますが、象印は1番大きくても加湿能力600ml/hとなっています。
そもそも「木造」と「プレハブ」って何?どっちを見ればいい?
加湿器のスペックによくある「木造〇〇畳/プレハブ〇〇畳」という表記、ちょっと分かりにくいですよね。
これは、建物の素材そのものだけでなく、「部屋の気密性や断熱性」の目安として見ることをおすめしす。
- 「木造」の畳数:
- 気密性・断熱性が比較的低い部屋を想定しています。
昔ながらの戸建て住宅や、築年数の古い建物、隙間風を感じやすいお部屋などがこれに当たります。
加湿した水分が外に逃げやすいので、小さめの畳数が記載されています。
- 気密性・断熱性が比較的低い部屋を想定しています。
- 「プレハブ」の畳数:
- 気密性・断熱性が比較的高い部屋を想定しています。現代のマンションやアパート、比較的新しい戸建て住宅などがこれに当たります。
水分が室内に留まりやすいので、大きめの畳数が記載されています。
- 気密性・断熱性が比較的高い部屋を想定しています。現代のマンションやアパート、比較的新しい戸建て住宅などがこれに当たります。
ご自宅がどちらか迷ったら?
一般的には、マンションにお住まいなら「プレハブ」を、戸建てにお住まいなら築年数や窓の断熱性などを考慮し、「木造」を参考に考えるのが無難です。
特に、加湿が心配な場合は、余裕を持って「木造」の畳数を基準にするのが、後悔のない選び方につながるかもしれません。加湿しすぎた場合は調整できますが、足りないとどうしようもありませんからね。
補足
エアコンや電気暖房がメインの方
これらは空気を暖める際に湿度も下げてしまうため、よりパワフルな加湿能力が求められます 。
石油
実はこれらの暖房器具は、燃料を燃やすときに水蒸気を発生させるので、加湿効果があります 。
そのため、エアコン暖房の部屋ほど高い加湿能力は必要ないかもしれません。
△「でも、本体の湿度表示は上がってるよ?」そのギモンにお答えします

「広い部屋だと力不足って言うけど、うちの加湿器の湿度表示はちゃんと上がってるよ?」と思う方もいるかもしれません。
これには、加湿器の湿度センサーの特性が関係しています。
加湿器に内蔵されているセンサーは、当然ながら本体のすぐ近くの湿度を測っています 。
スチーム式から出る温かい蒸気は、放出された直後は本体の周りに溜まりやすい性質があります。
そのため、部屋全体はまだ乾燥していても、加湿器の周りだけ局所的に湿度が高くなり、センサーが「部屋は十分に潤った」と判断してしまうことがあるんです 。
これが、「湿度表示は高いのに、なんだか部屋は乾燥している気がする…」という感覚の正体です。
正確な湿度管理をしたい場合は、部屋の真ん中など、加湿器から少し離れた場所に別途湿度計を置くことをおすすめします。
気になるポイント④:「電気代が高い」って聞くけど、どれくらい?
【結論から言うと…】はい、これはその通りです。他の方式と比べると、ランニングコストは高くなります。
◎ 事実として知っておきたい、水を沸かすための消費電力
これはもう、仕組み上避けられないポイントです。ヒーターでお湯を沸かすスチーム式は、他の加湿方式と比べて消費電力が一番大きくなります 。
例えば、象印の主力モデルEE-DC50(加湿時消費電力410W)で計算してみると…
- 1時間あたり: 約12.7円
- 1日8時間使うと: 約101.6円
- 1ヶ月(30日)だと: 約3,048円 (※電気料金単価31円/kWhで計算した場合 )
という計算になります。
△ データで比較!他の方式とのコスト差
他の方式と、同じ条件で比べてみるとその差は歴然です。
主要加湿器 電気代比較表
| 加湿方式 | 機種名 | 運転モード | 消費電力 (W) | 1時間あたりの電気代 (円) | 1ヶ月の電気代 (円) |
| ハイブリッド式 | HD-RXT525 | eco | 12 W | 約0.37円 | 約89円 |
| 標準 | 163 W | 約5.05円 | 約1,213円 | ||
| ターボ | 170 W | 約5.27円 | 約1,265円 | ||
| 気化式 | FE-KX05C | 静か | 4 W | 約0.12円 | 約30円 |
| 強 | 8 W | 約0.25円 | 約60円 | ||
| お急ぎ | 11 W | 約0.34円 | 約82円 | ||
| スチーム式 | EE-DF50-HA | 加湿時 | 410 W | 約12.71円 | 約3,050円 |
| 湯沸かし立ち上げ時 | 985 W | 約30.54円 | (参考値) | ||
| 超音波式 | ASZ-400 | (最大) | 30 W | 約0.93円 | 約223円 |
注:1ヶ月の電気代は1日8時間、30日使用した場合の目安です。スチーム式の「湯沸かし立ち上げ時」は運転開始直後の短時間における最大消費電力であり、継続的な運転コストは「加湿時」の値を参照してください。
衛生面や手入れの手軽さと引き換えに、ランニングコストは高くなる。このトレードオフを理解した上で選択することが大切ですね。
気になるポイント⑤:「運転音がうるさい」って本当?
特に夜間は人によっては結構気になる場合があります
でも「湯沸かし音セーブモード」である程度は静かにできます。無音ではありません。
◎ 避けられない沸騰音と蒸気音
お湯を沸かす以上、「コポコポ」という沸騰音や「シュー」という蒸気が出る音は、構造上どうしても発生します。
リビングなど生活音がある場所なら気にならないかもしれませんが、寝室のような静かな場所だと、気になる方もいるかもしれません 。
△ データと対策!騒音レベルと便利な機能
- 音の大きさの目安:
象印のデータによると、通常の沸騰時の音は約39dB。これは「図書館の中」くらいの静かさに相当します 。
- 音を抑える機能:
多くのモデルには「湯沸かし音セーブモード」が搭載されています 。
これは、水をゆっくり加熱することで沸騰音を約31dB(深夜の郊外レベル)まで抑える機能です 。
ただし、これは主に運転開始時の最初の湯沸かし音を抑えるもので、加湿中の再沸騰の音は変わりません 。
- お手入れも効果あり
内部にカルキ汚れが溜まると、沸騰音が大きくなることがあります 。定期的なクエン酸洗浄は、静かさを保つためにも有効です。
このように、運転音に関する対策はされています。
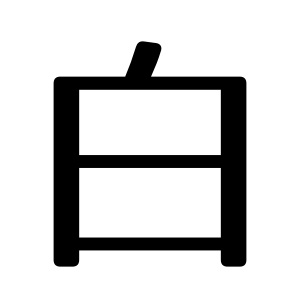
ただし、夜間の静けさというのもまた別格です。
アナログ時計の秒針が進む音すら気になる場合も有るくらい夜って静かなんですよね。
気になるポイント⑥:「安全性が低い」ってイメージがあるけど…
【結論から言うと…】メーカーの安全対策はしっかりしています。
でも、使う側の置き場所への配慮は絶対に必要です。
◎ 実は考えられている、メーカーの安全設計
高温の蒸気が出るので「危ない」というイメージがあるかもしれませんが、象印はその対策にかなり力を入れています。
- 約65℃に冷ました蒸気:
吹き出し口から出る蒸気は、沸騰した100℃のままではなく、約65℃まで冷ましてから放出されるようになっています 。万が一触れてしまっても、大やけどになりにくい工夫です。 - トリプル安心設計:
主力モデルには、お子さんのいたずらを防ぐ**「チャイルドロック」、倒れてもフタが開きにくい「ふた開閉ロック」、そして熱湯がこぼれるのを最小限に抑える「転倒湯もれ防止構造」が標準で付いています 。
△ でも、使う側の注意は必須
とはいえ、約65℃の蒸気も決して冷たくはありません。小さなお子さんやペットがいるご家庭では、絶対に手が届かない、安定した場所に置くという基本的な注意が大前提になります。
メーカーの安全設計と、使う側の正しい設置。この二つが揃って初めて安全は確保される、ということですね。
気になるポイント⑦:「結露しやすい」って聞くけど、対策は?
【結論から言うと…】加湿能力が高い分、結露のリスクはあります。
でも、置き場所を工夫すれば十分対策できます。
◎ なぜ結露するのか?
スチーム式は加湿パワーがあるため、部屋の広さに対して加湿しすぎたり、空気の循環が悪い場所で使ったりすると、空気中の水分が飽和状態になりやすいです。
その結果、温度が低い窓や壁に水滴がついてしまう「結露」が発生し、カビの原因になることがあります 。
△ 結露を防ぐための置き方のコツ
この問題は、置き場所を少し工夫するだけでかなり改善できます。
- 窓や壁からは離す:
外気で冷えやすい窓や壁の近くは避けましょう。これは基本です 。 - 部屋の中央あたりがベスト:
部屋全体に効率よく湿度を広げるため、できるだけ部屋の真ん中あたりに置くのが理想です。 - サーキュレーターとの併用が効果的:
サーキュレーターで部屋の空気をかき混ぜてあげると、湿度ムラがなくなり、結露防止にとても効果的です 。
結論:結局、どんな人におすすめなの?
ここまで、象印スチーム式加湿器の気になるポイントを色々と見てきました。これらの点を踏まえると、この加湿器がどんな人に合っているのか、その輪郭が見えてきたのではないでしょうか。
- 手入れの「洗いやすさ」と「蒸気の衛生性」は、他の方式にはない確かなメリット。
- ただし、「メンテナンスフリー」ではなく、定期的なクエン酸洗浄は必要。
- 加湿能力はスペック(加湿量・適用床面積)を冷静に確認する必要があり、特に広いLDKで使う場合は力不足になる可能性が高い。
- 「電気代の高さ」と「運転音」は、スチーム式である以上、ある程度は受け入れる必要がある。
- 安全性はしっかり考えられているが、使う側の置き場所への配慮は不可欠。
ネット上の「最強」という言葉だけを鵜呑みにせず、一度冷静に考えて貰えればよいかと思います。
いい製品だとは思いますけど、過信は禁物という感じですね。
では、今回はここまでです。




